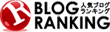『裏切り』の第二章。
「ごめんね……」
母が言った。
「……ごめんね」
母は泣きながら何度も何度も同じ言葉を繰り返していた。涙の数だけ繰り返されるその言葉を、そうやってぼくに伝えていた。涙があふれてこぼれるたびに指で拭う母だったけれど、それはずっと止まることはなかった。
「ごめんね……ごめんね……」
時おり、ぼくの名前も呼んでくれた。でもぼくはソファに座って前を向き、そのときやっていたテレビしか見ていなかった。『元気が出るテレビ』だった。はっきりと憶えている。
姉も隣で床に座って泣いていた。立ち上がることもできないぐらいに泣き崩れていた。母のそばへ這って行った。
奥にあるテーブルの、そのさらに奥では、椅子に座っている父が黙って床のどこかを見つめていた。向かい合って座っている祖母の言葉も、その存在すらも届いていなかった。テーブルの横には、もうゴミとなった料理や食器がぶっちらかっていた。でも父の視線は、そこを通り越しているようにも見えた。
祖母のひとり言のような声が聞こえていた。なにを言っているのかわからなかった。たぶん父に話しかけていたんだと思う。でも、そんなことはどうでもよかった。
やがて祖母が奥の椅子から立ち上がると、母のいるこちらに向かって歩いてきた。そのまま祖母が母の肩に手を添えてなにかをささやくと、母はその涙の音で崩れていくかのように立ち上がった。
「いつ帰ってくるの?」
そのときぼくが訊いた。
母は少し考えてから、答えた。
「一週間だから……すぐ戻ってくるからね」
ぼくは黙ってうなずいた。
「だいじょぶだからね」
その頭を母が優しく撫でてくれた。
「ごめんね」
そして母は、ぼくに背を向けた。ドアまでのあいだに、何回こちらを振り返ってくれたのか、ぼくは知らない。
「負けちゃダメだよ?」
祖母が、うつむくぼくの頭を触りながら励まそうとしていた。
「がんばるんだよ?」
涙がどんどんあふれてきた。しゃくりあげすぎて、息が止まりそうだった。でも、一粒も落とさなかった。
顔がグチャグチャになっても、なぜかずっと我慢していた。
「……やめてくれ」
それまで黙っていた父が祖母の手を止めさせた。
それは、ぼくも言いたかった言葉だった。心のなかでそう願っていた。
父の目は真っ赤に充血していた。怒りじゃない。眠たいわけでもなさそうだった。父は心のなかで泣いていたんだ。
「 ──── もう行ってくれ」
その父の静かな言葉に、しばらくのあいだ顔をそちらに向けたあとで、祖母は、ドアのところでこちらに横顔を向けて待っている母のもとへと歩み寄っていった。
そしてそこからもう一度、ぼくを振り返ってこう言った。
「強いね、拓弥は……」
そして最後にこう付け加えた。
「……偉いね」
どれだけ涙を流したろう。
なにも偉くなんかない。全然強くなんかない。
もしも涙がなかったら、どうやって弱さとか強さとか、優しさだとかを表現したらいいのかわからない。
涙がそれを連れてくる。弱いから泣くんじゃなくて、泣かないから強いんじゃない。
涙そのものが理由になっているのかもしれない。
いつも涙が涙を呼んでくれる。弱さも強さも、優しさも。
もしかしたら、これはすごく深くて大きな傷となって、いつまでもぼくの心に残るだろう。
でも、それが痛んで泣いたことより、自分のそれよりもっと大きな弱さを知った。
あのとき母を抱きしめてあげたかった。でもぼくは、くずれてゆきそうな自分を支えるだけで精一杯だった。ただ黙ってうつむいて、涙を我慢することしかできなかった。我慢することが、ぼくのなかの強さだと思っていた。
でも、それは間違いだった。最後まで強がりたかっただけだった。
「男の子なんだから泣くんじゃないの」
母に何度も言われた記憶がある。それをぼくは必死になって貫こうとしていたのかもしれない。
でも本当の理由はわからない。
でも、そんなことはどうでもいい。
ぼくがやっとテレビから顔を向けたとき、すでに母の姿はそこにはなかった。玄関フロアの電気もつけずに出て行ったその扉のむこうには、居間から漏れるわずかな光しか届いていなかった。
暗かった。
そして、静かだった。
ただ、いつまでも母の涙の声が聞こえてくるようだった。
- 2008年10月31日 07:21
- ──── 『裏切り』
- Newer: 裏切り : 第三章【写真】
- Older: 裏切り : 第一章【バイバイ】