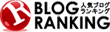『裏切り』の第四章。
「ごめんね……」
それから一週間が経ってすぐに、ぼくは母に電話した。
「……ごめんね」
母が言った。顔の見えない電話の向こうで泣きながら、また何度も何度も繰り返した。
あの日と同じことの繰り返し。
ぼくは電話を切ったあと、もう泣くのをやめた。
泣いてもなにも変わらない。泣いても母は帰ってこない。
もう帰ってこないことはわかっていた。ただ、最後に、それを最後に、母のことを忘れてしまおうとしていたのかもしれない。でも、それもムリだということも、わかっていたと思う。
それからぼくは、学校から帰ってきても家から出なくなっていた。わからないけど、外に出て友達と遊ぶよりも、ぼくは家で待っていた。なにを待っていたのかは、わからない。父もいなくなったらどうしよう。もしかしたら、母が帰ってきてくれるかもしれない。そう信じていたのかもしれない。
でも、ただひたすらなにかを待っていた。
いつからか、ぼくは母を憎むようになっていた。
もしかしたら、そうじゃないかもしれないけれど、好きと言えないのはたしかだった。
母は死んだと、ぼくは思いこむようにした。生きているのは知っていたし、姉が電話もしていた。だからぼくは、死んだというより、母のその存在自体がなかったんだと、自分にそう言い聞かせていたのかもしれない。それで自分を納得できたなら。
そのほうがラクだった。やっと少しはラクになれた。
でもそれは、ただ逃げだしたかっただけだった。毎日まいにち母の影を追いかけて、それをどうにか理解しようと必死になっていることに疲れてしまったんだと思う。背中を向けられて、ぼくも同じところに背中を向ければ、同じところは見ないですむ。
振り返ってくれるのを待っているより、ぼくは、ぼくが振り向かなければそれでいいと。
母はいつも謝った。
“ ごめんね ” って言う言葉を憶えている。今でもはっきりと耳の奥に焼きついている。
それが母の言葉だった。
それが僕を、より深く傷つけた。
何度も何度も謝ったからってすむことじゃない。
ぼくはいつからか、そんな母を憎むようになっていたのかもしれない。
そのたびに悲しくむなしくなったけど、記憶に残る母の影を追いだそうと、いつも過去にもがいているぼくがいた。想い出だけを残して去ってゆくなら、母親なんて最初からいないほうがよかったとまで思ったこともあった。
でも想い出が悪いんじゃない。それを憶えているのがイヤだった。忘れられないのがつらかった。
でも母がいなければ、その想い出すらもない。
いや、まず、ぼくがいない。
“ ごめんね ” っていう言葉も嫌うようになっていた。
謝ることは負けることだと思っていた。
でもそれは、本当の気持ちを伝えることだとわかったとき、ぼくは心のなかで謝った。
素直になるっていうそれも、一つの “ 強さ ” なんだと呼べることだと知った。
でもそれは、ずっとずっとあとになってからのことだった。
- 2008年10月31日 07:48
- ──── 『裏切り』
- Newer: 裏切り : 第五章【ありがとう】
- Older: 裏切り : 第三章【写真】