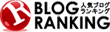『裏切り』の第八章。
母からの手紙を居間の大きな棚の抽斗で見つけたのは、さらにだいぶ経ったころだった。
ぼくらのことは書いていなかった。二回読んでも、三回読んでも同じだった。
ぼくは、母のなかからぼくらの存在も消えたんだと感じた。もう泣きはしなかった。
ただ、ぼくのなかでも、なにかがすっぽりと消えてしまった。
母からぼくに宛てた手紙も届くことはなかった。
いつの間にかぼくのなかで、母のいない生活があたり前になっていた。
友達の家に遊びに行ったときにうらやましいとは思わなかったし、参観日はあってもなくても同じだった。ただのその教科の授業の日だった。
「おまえのお母さん、なんでいないの?」
そのようなことを友達に言われても、嘘をつく気もなかったから、ぼくはそのままのことを友達に伝えた。ただ、どんなに仲がよくても、それを自分から話すことはなかったけれど。
そして今まで、自分の親のこと、家族のことを話した人は友達でも恋人でも、ほとんどいない。
でも、忘れたわけじゃない。ただそれが、ぼくのなかでの “ 普通 ” になったというだけのことだった。
でも、間違っていた。
そして、そのことに気づくのが遅すぎた。
今思えば、だからこそ、そこにはぼくらへの想いがいっぱい詰まっているんだと、そのとき読むべきだった。母が流した涙の雫が、そこにある文字の数だけ、いや、それ以上ににじんでいるということを。
できればぼくは、ずっと母を憎んでいたかっただけなのかもしれない。憎める相手がほしい。憎むことで、ずっとその母の優しさに甘えていようと必死になっているだけなのかもしれない。
いつも歩き慣れた道でなければ、ぼくが歩けなくなっていたのかもしれない。
いや、いつもの道すら怖がるようになってしまっていたのかもしれない。
- 2008年10月31日 08:56
- ──── 『裏切り』
- Newer: 裏切り : 第九章 【 安心 】
- Older: 裏切り : 第七章 【 涙 】