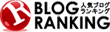『裏切り』の第九章。
もしあのとき、母と一緒に行っていたらと思うことがよくあった。むしろ、そっちのほうがよかったんじゃないかと感じることが多かった。
ぼくは母が好きだった。いつも明るい母が大好きだった。だれより優しい人だった。親だからっていうのもあるかもしれない。でも、それとは別にも優しかった。だれにも優しい人だった。
でも、ぼくは父を選んだ。
幼いながらも、セコい計算をしてたと思う。母と一緒に行けば、間違いなくゆとりのある生活はないと想像できたし、やりたいことにも制限が出てきていただろうと。
でも父といれば、少なくとも、母といるよりは生活はマシだと、ぼくはそんな答えをだしていたんだろう。
あの日母はぼくを捨て、それと同時に、ぼくも母を捨てたんだと思う。
でも後悔はしていない。
もしもそれがあるのなら、それは、あの日ぼくが母になにも言ってあげられなかったことだ。謝る母に、涙を流す母に、そして母に、ぼくはなにもできなかった。
「ごめんね」
ぼくも心のなかで同じ言葉を繰り返していた。ただそのときは、なにより自分が精一杯で、どうしようもない自分を閉じこめた。怖くて、不安で、今すぐそこから消えてしまいたかった。
「だいじょうぶだから」
そんな強がりさえも閉じこめた。
もしも母といたら、今のぼくはいない。
きっと母がすべてになってしまっていると思う。今の母との関係みたいに、ちょくちょく会いに行ったりすることもできず、きっとずっと父を憎みつづけていただろう。
父は怖い。厳しい人だ。だからその怖さがどこかでさらに大きくふくらんで、父にはきっとずっと近づけなかっただろうと思う。
ぼくは、父と一緒にいたかったわけじゃない。母にずっとそばにいてほしかっただけじゃない。
ぼくは、父と母と一緒にいたかった。
もしかしたら、この先どこかで過去とか想い出なんかが、ぼくの足かせのように感じてしまうことがあるかもしれない。不安もある。
そして今、こうやって書き綴ってきていながら、それは、キレイないい面しかないことに改めて気づいてしまう。
美談になるようなことばかりでもない過去なのに、ましてや、こんなふうに人に語れることでもないのに、それがまるで美しいもののように書いてしまっている。
でも想い出は、自分じゃそれを色褪せさせることも難しくて、いつまでも美しくて、そして、深いところにある。だからこそ、今でもこうして過去やそんな想い出に縛られてしまっていると、そんなふうに思えることがある。
いや、美しい部分だけを残しておこうと、これが最後までつづくぼくの悪あがきなのかもしれない。
でもぼくは、それでいい。
- 2008年10月31日 09:10
- ──── 『裏切り』
- Newer: 裏切り : 第十章 【 後悔 】
- Older: 裏切り : 第八章 【 空白 】