『裏切り』の第十章。
それまでぼくは、ずっとなんだかんだともっともらしい思いつく限りの嘘をついてまで、それを断りつづけていた。
でもぼくは、その日初めて母に逢いに行った。
なにがそうさせたのはわからないけれど、なんとなく、そろそろいいかなということで承諾していた。でもなにが “ そろそろ ” なのかもわからない。
ぼくは筆舌に尽くしがたいほどの動揺っぷりを露呈してしまっていたと思う。
母に逢いに行くというのに、スーツのほうがいいか普段着のほうがいいかと、姉に訊いたりしていた。緊張はもちろん、そのへんのモノに当たり散らしたくなるほどイライラもしていたし、漠然とした不安があった。
前日ぼくはほとんど眠れないまま、次の日、姉の運転する車に揺られていた。
到着すると、そのときはちょうど夏休みの時季で、母方の親戚たちが来ていた。おしゃべりやらテレビゲームやら、そんなにぎやかななか、ぼくは入口のすぐ前に黙って座っていた。
祖母に話しかけられても、ほとんど聞こえてはいなかった。相槌すらろくに打てずにいた。姉はもうほとんど無視していた。でも、両足を伸ばし、両手を背後についた格好で、態度だけはデカく見せてようと努めていた。
それがぼくのせめての虚勢だった。
やがて母が居間の扉を横に開いた。
一瞬ためらったあとぼくが振り返った。
一人ひとりを数えるようにそこにいた人の上を母の視線がなぞっていった。
そしてぼくと目が合った。
と同時に、母の目からは涙の粒がぽろぽろと、その頬の上をこぼれていった。
と同時に、ぼくは視線をそらした。涙の我慢をつづける自信がなくなった。
「どうしたの突然……」
母は、まるで船の帆がたたまれていくかのようにその場に腰をおろし、ぼくのスーツの袖をかるくつかんだ。
「……言ってよぉ~、びっくりした」
姉は笑っていた。
「よかったね」
「最高だ」
母は祖母に、テレビで見る田舎者まるだしの口調で、笑いながら大きく何度もうなずいてそう伝えた。
「元気だったかい?」
「ああ、元気だったよ」
「そうか……そうか……よかった」
「ああ、そうだ」
ぼくは母ともまともな会話ができずにいた。
それでも母はそこから動かなかった。そして、ぼくの横顔をまじまじと眺めては、この角度はそうだとか、そのしぐさは確かにそうだとか、いちいち本当にぼくなのかを確認しては泣きながら笑っていた。
「ホントにそうか?」
「ホントにそうだって」
そんなやりとりが繰り返されて、ぼくも自然と笑っていた。
「ホントにか?」
「ホントだって」
その後も、あたり前のような母からの質問がつづいた。
その質問に答えていくたびに、言葉が詰まってどれもひと言かふた言だけだったけれど、ぼくのなかに渦巻いていた疑問が、一つ、また一つと霧散していった。
「なんか欲しいものとか、なんかしてほしいこととかない?」
母がぼくに訊いた。
「帰ってきてほしい」
ぼくはその言葉を必死になって飲みこんだ。
しばらく考えてから、こう答えた。
「……膝枕」
それからぼくは帰る時間になるまでのあいだ、母のその膝の上で目を閉じた。安心したから、そのまま眠ることができたんだと思う。
でもやがて、その時がきた。
姉は、ぼくと母に気を遣ったのか、車を持ってくると言ってぼくの返事も聞かずにすぐに玄関口から出ていった。
一歩下がったところに母が立っていた。
そこに着いたときからずっとあった “ 帰りたい ” という気持ちは、もうすでになくなっていた。でも、それ以上そこにいたら、今日は絶対に泣かないと決めていたことは守れそうになかった。
ぼくは玄関の戸に映える夕陽の明かりをぼんやりと眺めながら靴を履いていた。
それはあまりに突然だった。
母がぼくの背中をつかんだ。そして、ぼくの名前をぽつりと呼んだ。
片足で立っていたぼくは、危うく前に倒れそうになった。でもそのまま倒れていかなかったのは、母がそれだけ強く、ぼくにしがみついていたからだった。
「……ごめんね」
全然イヤだったわけじゃない。
「わかったって」
でもぼくは、そう言って居心地悪そうに肩をひねってしまっていた。
「危ないから」
ただ恥ずかしかった。
「ほら、靴、履かないと」
本当はすごく嬉しかった。そんな自分が恥ずかしかったんだ。
「そうだね」
母は涙を飲みこみながら、ぼくの背中から顔を離した。でもその袖は強くにぎったままだった。
「……ごめん」
「いや」
少し高くなっているところから下におりて、ぼくは母を振り返った。
「だいじょうぶだから」
それがぼくの精一杯だった。
あとからついてくる母に見守られて姉の車に乗りこんだぼくは、ドアを閉めながらその窓を開けていた。
急がずゆっくりとこちらに向かって歩いてくる母の姿を眺めていた。
正直に言ってしまえば、ずっとそこにいたかった。
学校も行きたくなかったし、友達とも離れたっていいとまで思っていた。たまに会うのは父のほうでよかった。玄関で振り返ったときの母の表情に、ぼくは後悔した。
抱きしめたかった。母がしてくれたように、ぼくもこの腕に母を力いっぱい抱いてやりたかった。
「またおいで」
窓のむこうから母が言ってくれた。
「ああ」
「じゃあ、気をつけてね」
「ああ」
「じゃあね」
「ああ、また」
ずっと正面を向いていた方向にゆっくりと車が進みはじめた。
「 ──── あ、待って」
ぼくは姉に言った。
「ちょっと戻って」
また母のところまで姉が車をバックさせた。
「なした?」
「ちょっと待って」
ぼくは、自分のスーツについているすべてのポケットを探ってから、そこから鍵の束を取りだすと、ずっとそれにつけていたキーホルダーを窓から母に手渡した。
「はいこれ。あげる」
「いいの?」
「ああ、いいよ。なんもしてやれなかったから、せめてね。今はその小汚いキーホルダーしかないけど……おれだと思って大事にしてやって」
「うん ──── 大事にする」
母は、それを自分の胸に両手で押しつけて、流れる涙を拭うこともせずに、笑いながらそう言ってくれた。
「ずっと大切にするから」
ぼくはその日、母に逢いに行ってよかった。
だから、いつもぼくを誘いつづけてくれていた姉にも感謝したい。
本当に、逢いに行ってよかった。
母は今でもそのキーホルダーを使ってくれている。
その日を最後に、母を憎んでいたぼくが消えた。でもそれは結局、最後まで母を憎みきれずにいたぼくだった。
- 2008年10月31日 09:33
- ──── 『裏切り』
- Newer: 裏切り : 第十一章 『 たったひとりのひと 』
- Older: 裏切り : 第九章 【 安心 】
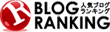












サインインはオススメしません。