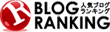『裏切り』の第十二章。
「じゃあ、拓弥にとっての “ 家族 ” って?」
ぼくの答えに、母は助手席からそう言った。ぼくにとってのそれを訊いた。
母が煙草を一本抜き取るのを見て、ぼくも同じことをした。
「難しい質問だなぁ~……」
そう曖昧に間を取ったのは、そのときぼくの心臓がなにか強い力で鷲づかみにされたように、一瞬その血液を止めていたからだった。
「……なんかこう、書くっていうのが好きみたいなんだよね……で、どうしても書きたいテーマっていうか、そういうのがあるんだよね」
「なに?」
「 “ 家族 ” 」
それまでの会話から、絶対にそこを聞かれるとは思っていたけど、その答えは用意できていなかった。いや、あったけれど、それをすぐには出せなかった。
それを落ち着かせようとも思って、ぼくは「う~ん」とか「ああ」とか一人でうなりながらしばらくのあいだその答えを考えていた。母に気を遣ったような答えをしようともしたけれど、でも、それはやめた。嘘をついても仕方ないし、母にはもういつも素直でありたかった。
「……一番近いけど、一番遠い存在……」
「そっか……」
と、母はぼくにも聞こえるか聞こえないかぐらいの声でつぶやきながら、吸っていた煙草を灰皿で消した。そのあと、ほんの少しその視線が下を向いたような気がした。
「……憧れ、かな?」
すぐにその言葉に変えたけど、気をきかせたわけじゃない。それも素直なぼくの気持ちだった。
でもそれが逆に、母の沈黙の時間を伸ばしてしまっていたのかもしれない。
しばらくのあいだは、ぼくも窓の外を流れてゆく景色に意識を向けた。
ぼくは運転があまり得意なほうじゃない。ぼくは何度も同じところをグルグルとまわっているらしかった。
姉の車を借りて、一人で母の働いている店にその日の夕飯を食べに行ったときのことだった。食べ終わって母と話しているあいだに、もう閉店の時間になり、ぼくも帰ろうとしていた。母は自転車で通っているみたいだったけれど、それを店に置いて、ぼくが乗っていった車の助手席に乗りこんだ。最初から送っていく予定だった。
少し走ったところで、ふと母は思いだしたように言った。
「ちょっとドライブしよう」
「いいよ」
それから母と他愛のない話をした。仕事のこと、将来のこと、父や姉のことなど、ごくごくありふれたことだった。
「あんたは一人じゃ絶対、生きていけない人だからね」
ぼくの恋人との話題になったときに、母が言った。
「一見孤独を愛しそうに見えるけど、実は全然違うから……人一倍強がるけど、人一倍弱くて、すごくもろい部分あるからね」
言葉がなかった。
ぼくは、弱い。そして、もろい。
むなしいだけの強がりの嘘を重ねてきた。自分ではあまりよくわからないけれど、きっとそれは当たってる。
「そうかもね」
正直、驚いた。そして、嬉しかった。母はわかってくれていた。
だから母は、そのあいだ中ずっとぼくが涙を必死になってこらえていたことにも気づいていただろうと思う。
今でも母の影を探してしまう。求めてしまう。
でもそれは、母の愛を知らないからじゃない。むしろ、何より一番知っているからだと、ぼくは思う。知らないものは見つけられないし、求められない。求められる相手もわからない。
ぼくが泣いてしまったとき、ぼくをその手に抱きしめて一緒に泣いてくれた母のぬくもり。その優しさを。
それがなぜかは、自分だけじゃわからなかっただろう。
すごく時間がかかった。かかりすぎた。
そうやって改めて母に会ったとき、会えるようになったときに、それがやっとわかった。
母は、ぼくをわかってくれていた。あたり前のことかもしれないけれど、ぼくのことを知ってくれていた。
でもぼくは、母の気持ちをわかってやれてはいなかった。
あの日の母の気持ちをわかっていなかった……母は、母だったんだと。
そして今も……そんな単純なものじゃなかったはずだから。
でも、そこには一緒に涙を流せるほどの絆がある。
母は母で、ぼくはぼくでも、本当に相手のことを信頼していなければ、絶対に自分の弱みは見せないのは、親子そろって同じだから。
- 2008年10月31日 09:57
- ──── 『裏切り』
- Newer: 裏切り : 第十三章 【 父 】
- Older: 裏切り : 第十一章 『 たったひとりのひと 』