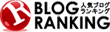『裏切り』の第十三章。
「ああ、もしもし、親父?」
「おう」
「元気か?」
「おう、元気だ。おまえはどうなのよ?」
「ああ、おれも元気でやってるよ」
「そうか。それならいいんだ」
「それならおれもいいんだ」
「なした?」
「いや、別に……」
「それだけか?」
「それだけで電話しちゃ悪いか?」
「いや、悪かないけれどよ……たまには帰ってこいよ?」
「ああ。ほんじゃな」
「おう。体にゃ気をつけろよ?」
「ああ、親父もな」
「おう。じゃあな」
「おう」
でも今、いろいろなことを自分なりに考えられる年になって、こんなふうに感じる。
きっとあのとき支えが必要だったのは、母より、父だったのだと。
泣いてぼくらに何度も何度も謝って、ずっとぼくらのことを想ってくれてた母よりも、謝ることすらできなくて、きっと孤独になるだろう父のそばにいるべきだと。それから改めてひとりになって父親ヅラをしようと一生懸命がんばる父のそばにいてやりたいと。
そして父は、本当に、本当にがんばってくれた。
なにか相談に乗ってくれたりとか、どこかいろんなところへ連れていってくれたり、たくさんおもちゃを買ってくれたりしたわけじゃない。ただ、父は、厳しさをもって、父なりのやり方で、一生懸命にぼくらに接してくれた。
母が出ていくまで、父が泣いた姿は一度も見たことがなかった。
でも、それからは、今までに父のそんな姿があった。本当に何度かだけれど、父は、ぼくの前で涙を流した。
そして、わかったことがある……父は、人一倍厳しい人だけれど、人一倍優しい人なんだと。
全然素直じゃないし、つっぱった態度で勘違いもされやすいけど、それが父だとわかった。だれよりさみしがりな父だったんだと、父の涙が教えてくれた。
不安だったんだ。父も。
「もう親だなんて思わなくてもいいぞ?」
父は我慢しきれない涙をポツリポツリとこぼしながら、ぼくにそう言った。
ぼくは心のなかで吐き捨てた。
<もう最初っから親だなんて思ってねえよ>
またある日には、こう言われたこともあった。
「殴れ? 遠慮すんな? ほら、殴れって」
と、父はメガネをはずし、血走った眼でぼくを睨みあげていた。
正直、ぼくはそのとき一瞬だけ迷った。
「……殴れない」
「なんでよ?」
「親だから……」
言う気もなかったし、声にも出しはしなかったけれど、ぼくのその言葉には、まだ先に続きがあった。
……殺せない。
そのときは、ここで一度父を殴ってしまったら、自分でも歯止めがきかなくなってそのまま殺してしまうかもしれないと本気で感じた。
こんなつまらないことで少年刑務所なんて行きたくないとまで思っていたかもしれない。怖かった。
今までにも、拳で人を殴ったことがない。小学生だったころのケンカでも、そんな記憶はない。
だから、自分でもどうなるかわからない。もしかしたら、潜在的にそういった暴力に快楽を覚えるようなサイコかもしれないし、そうじゃないかもしれない。わからない。
でもきっと、今だから言えることかもしれないけれど、あのとき父を殴っていたら、そのまま殺してしまっていたと思う。少なくとも、父には生きてる気がしないほどに殴っていただろう。
けれど、今は違う。
父は父だ。
当時は本気で殺意を覚えるほどに憎んだこともあったそんな父でも、好きなことには変わらない。
これはただの結果論かもしれない。あるいは、自分に都合のいいように考えようとしているだけなのかもしれない。あるいは、自分に都合のいいように考えられるようになったのか。
いつか父に逢いに家に帰ったとき、父がなにげなく差しだしてくれた手。
「元気だったか?」
「ああ。おやじは?」
「おう、元気だな」
とそのとき、はにかんだような微笑みで交わした固い握手は、今でもずっと忘れられない。力強くて、優しかった。
だから父には、ずっとそのままでがんばってほしい。
- 2008年10月31日 10:12
- ──── 『裏切り』
- Newer: 裏切り : 第十四章 【 絆 】
- Older: 裏切り : 第十二章 【 家族】