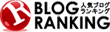『裏切り』の第十四章。
ぼくは、両親のふたりともが好きだ。
高価な時計やプレゼントができるわけじゃない。旅行に行かせてあげることもできないだろうし、家を建ててあげることだって、きっとできない。
でも、心のなかのどこかに、いつも父と母をひっかけている。それがぼくなりの親孝行だと思っている。
だからそれ以上のことは、あまり期待しないでほしい。ぼくがもし、なにかできるようになるまでは(笑)
“ 血は争えない ”
よくそう言われるけれど、ぼくはそうは思わない。思えなくなっていった。
絶対になにがあろうと父を悪く言ったりしなかった母を、父が、たまに悪く言ったりしたとき、そんな父に対してすごくムカついた。生まれて初めて殴るのが父になるところだった。そのほかにも、そんな場面が何度もあった。
逆に、本当に母を憎んでいた日のいつかなら、なにかの拍子で間違って刺していたかもしれない。もし帰ってきたとしても、そのタイミングが悪ければ、その存在を無視したかもしれない。
血が争いを招くということはあるかもしれないし、自分の体に流れている血を呪うこともあるだろう。ぼくはそこには、人がそう言うだけのそんな大きな絆があるとは思えない。
血はあくまで部品みたいなもので、それがさらに大きなものを生みだすんだと思う。
ちょっとほかの部品よりも生産性が高いっていうだけなのかもしれない。ラベルにある “ MADE IN ” っていうのと大差ない。ただぼくという人間を構成する部品の一つにすぎない。
だから離婚が原因で嫌いになったりはしない。一緒に住んでいても、だれよりもそばにいたとしても、嫌いにはなれる。でも離れ離れになってしまったからといって、そこにあった絆までが消えてしまうわけじゃない。
それが血だと言う人がいるなら、それでもいい。
でもぼくにとっては、それは、なんの理由にもならないし原因にもならない。
血がどうのこうの言う問題じゃなくて、ただ父と母が好きなだけなんだと思う。
ぼくが大切にしたいのは、そこにある絆だけでいい。
- 2008年10月31日 10:19
- ──── 『裏切り』
- Newer: 裏切り : 第十五章 【 自分 】
- Older: 裏切り : 第十三章 【 父 】