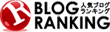『裏切り』の第十五章。
1回。
2回。
3回。
“ なにやってんだろう? ” と自分で感じながらも、これを書きながらぼくは、自分が泣いた回数をメモしていた。やっぱりぼくは泣いてしまっていた。
そんな母に対する自分の想いに、一つの区切りとしての意味もこめて、ぼくはこれを書いてきた。
時間があるときには自分から母に逢いに行こうと思えるようになり、母と話していても自然と笑えるようになった。ちゃんと母の顔を見て、会話できるようにもなった。だから自分のなかで、母に対しての照れが生まれたり、気遣いができるようになったのかもしれない。自分の心のなかのどこかに、いつの間にかそんなゆとりができていたのかもしれない。
母もあまり涙を流さなくなった。ただ我慢しているだけなのかもしれないが、逢いに行ったときには、ぼくと笑って話していることが多くなった。
それでいい、そうやって笑って話してくれてありがとうと、今ではその過去を自分の過去の一つとして、冷静に見つめることができるようになったぼくがいる。
でも、まだまだ成長できていない面というのも認めざるを得ない。
その母の笑顔を、やはり “ 裏切り ” と感じてしまうことがある。
前に進むことも、戻ることもできない、あの日のままのぼくもいる。
必死に成長しようと、いつも背伸びしてしまっていたのかもしれない。仕方のないことなのだと、ムリに自分のなかにある感情を片付けてしまうことのできなかった自分が、情けなかったのかもしれない。そこの一点に固執してしまっていたのだろう。ただ漠然としたなにかに焦っていたのかもしれない。
二十歳をすぎてもマザコンな自分がいるのだ。
過ぎていった時間のおかげかもしれないし、いろんな人との触れ合いのなかで、ぼくのなにかが変化していったのかもしれない。
あるいは、もしもこれから先のいつかに、母と同じことをしてしまうかもしれない自分を、こうして弁護しようとしているだけなのかもしれない。母を許して、いつかの自分をも許そうとしているのかもしれない。
そしてそれが、そんな自分に対する欺瞞であるだけなのかもしれない。
自分自身を問い詰めていくと、いつまでもキリがない。その答えも見つからない。
でも今のぼくは、そうやって少しでも成長しようと、たった一歩でも前に進もうとしている過程にあるのかもしれない。まるでいろんな自分がいるようだけれど、でも、どれもぼくだ。
どれが嘘で、どれが本当ということもない。
本や映画で見て憧れたりもしたけれど、それとは違う。ぼくにはちゃんと記憶がある。忘れたりはしない。できない。
なにもかもを許せたわけではない。
でも、なにもかもを母のせいにはしたくない。
今でも、“ なぜ? ” ということを訊けないでいる……
なぜ、出て行ったのか?
ぼくにその答えを聞くだけの余地がないかもしれない。しっかりと受け止められるかもしれないし、耳をふさいでしまうかもしれない。聞かなかったフリをするかもしれない。あるいは、また元の自分に戻ってしまうかもしれない。
間違っているとはわかっていても、もし自分の期待していた答えと違っていたときの自分が想像できない。自分を責めるか、母を責めるか。また閉じ込めてしまうのか。
気遣いや笑顔のゆとりはあっても、それはまだそれだけで、小さすぎるのだと思う。勇気もない。
そして何より、なにもかもが主観的で利己的すぎる。母の立場になって考えるということが、今だにできないでいる。
母ではなく、ぼくが一番そこに背中を向けてしまっているのかもしれない。
いつも不安がつきまとう……そこに本当の裏切りがあるのではないかと。
母は、そんなぼくの不安は笑い飛ばしてくれるかもしれないし、違うかもしれない。自分のその弱さやそんな小さな期待のせいで、母を本当に失ってしまうことになるかもしれないのだから。
でも、それも乗り越えたい。なにも疑うことなく、からっぽのまま素直に笑って話せるようになりたい。
そんなふうに早くそこから脱したいという気持ちがある反面、そのままでいいという安心もある。
ぼくのなかの甘えが消えない。
強くなったと胸を張って逢いたいけれど、時には膝枕もしてほしい。そのへんが母の言う、ぼくの弱さなんだろうと思う。自分でもそう思う。
かなり大雑把ではあるけれど、自分で料理をしていて母の味に似てるかなと思いだしたときは、嬉しかったり恥ずかしかったりする。でも、それに少しさみしさを覚えるから、あまり味見をしないようになってもいたり。
ぼくは、今になっても母へ対する自分の気持ちがわからない。
自分の気持ちすらわかっていないのだから、母の気持ちも同じだろう。
“ でも ” ばかりを繰り返してしまうのがそれを明確に示しているように、ずっとどっちつかずで中途半端なままでいる。
でも、それでいいとも思っているのかもしれない。
こういう自分の気持ちには、いつまでも決着なんてものはつけたくない。母と笑いながら話ができるようになった今でも、そしてこれからも、この涙だけはずっと流していたいのかもしれない。
今ある気持ちを大事にしたい……わかっているだけでいい。いや、本当はそれだけで充分なのかもしれない。
「元気だったか?」
「ああ」
「ちゃんと食べてるの?」
「ちゃんと食べてるよ」
「風邪とかひいてないかい?」
「うん」
「あのお友達のコは?」
「元気だよ」
「じゃあ、元気でやってんだね?」
「ああ」
「よかった」
母に会うといつも、ほとんど同じ会話ばかりになる。
その母の気持ち、そして、この自分の気持ちを裏切ることのないように、これからもぼくはぼくなりの、ぼくのままでいいようと思う。
これは “ 追憶 ” とか “ 想い出 ” なんかじゃないかもしれない。
それはたしかに過去だけれど、それは今にも生きているのだから。
母に会うたびに、そして、今こうして過去のなかにある記憶の糸をたどってゆくたびに、ただそれだけでも、涙がどんどんあふれてきてしまう。
そしてぼくは泣いてしまう。
今でもちゃんとはっきり憶えてる。
怒ったときに、下唇を噛んでしまうそのクセも、寝グセをだれにも見せないことも。煙草はセブンスターで、その色にはまるで合わない安い黄緑色のライターを使っていたことも知ってる。パジャマは淡いピンク色だった。メガネも服もありきたりで、自分の見た目は全然気にも留めない人。よっぽど信頼できる人じゃないと、自分の弱みを隠そうとするところがあった。
そして何より、ホントに素直な人だった。無邪気に笑った顔が好きだった。
ぼくはそんな母が好きだし、ぼくにとっては、たったひとりのひとだ。それは父も同じだ。姉もそうだけど、姉はもう友達みたいな感覚だから、これまでも、これからも、特に心配なんてしていない。
大切なものに、順位なんてつけられない。
それはなにも母や父や姉にだけ言えることじゃない。いつもずっとそばにいてくれる親友も、みんなぼくの大切な家族だ。
ムリやりぼくを捨てた母。ムリやり笑おうとしてくれた父。ムリやりにでもぼくを母に逢わせようとしてくれた姉。ムリをさせてしまっても、ぼくを支えてくれた恋人たち。ムリなことを言っても、ぼくといつも一緒にいてくれた親友。
だから今度は、ぼくの番だ。
自分を犠牲にしてまでムリをしようとは思わないけれど、ぼくの大切な人には、できればいつも笑っていてほしい。
もう怒鳴り声は聞きたくない。
大切な人の涙も、自分が流す涙も、これ以上は見たくない。
嬉しいときの涙は隠さず流せるようになりたい。
そこにある現実に背を向けてしまうこともしたくない。それはこの先も難しいかもしれないけれど、ぼくはやはりそうありたい。
笑っていてくれれば、それでいい。ぼくの大切な人には、いつも笑っていてほしい。
それがぼくの一番の夢であり、憧れなのだから。そして、それがぼくの家族であってほしい。
だからもし、“ 追憶 ” と呼べるのは、あの日あのときにできてしまったぼく、つまりあの日からずっと “ 変わらない自分、変われない自分 ” というその存在だけなのかもしれない。
- 2008年10月31日 10:40
- ──── 『裏切り』
- Newer: 裏切り : 第十六章 【 今 】
- Older: 裏切り : 第十四章 【 絆 】