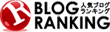とある女の物語。
学校までの道。
夕暮れどきにはカラスがどこか知らない場所へ鳴きながら飛んでいき、雨の日にはなんとも言えないほど不気味に見えた。どんよりとした重苦しい曇りの日には、まだ見えてもいないのにその先にある学校の校門に睨まれているような気がして行く気がしなかった。
わたしはいつもその道を通って小学校に行っていた。
小さな家が連なって自然とできあがった、小さな町の小さな道。
気分のいい日には鼻歌でも鳴らしながら、ひとり、テクテクと人形みたいに歩いた道。友達とケンカした日には、道の小石を蹴飛ばしながら帰った道。
けれどある日、ふとその家の石塀に手をこすっていた。興味がわいて触りたかったわけでもない。ただ触れてしまっていたらしかった。
それまではそんなところに、そんな家があってそんな石塀があることすら知らなかった。間違いなく見たことはあった。でも特に意識したことはなかった。もしかしたら、その塀の上にカラスが止まって鳴いていても、“羽根を閉じて飛んでるんだ”と見えたかもしれない。
なにはともあれ、その日、わたしの手はその石塀に触れてしまったのだ。
その次の日から、わたしは、その道を通るときは必ずその石塀を手でなぞりながら歩くようになっていた。次の日もその石塀に手をこすっていた。その次の日も……その次の日も、そのまた次の日も……学校が休みの日には、その道を通って友達の家へ遊びに行っていた。
しかしその習慣は、やがてわたしがその道を通らなくなった日を境に終わった。
父の転勤が決まった。突然だった。
「本社だ」
そう静かに告げたときの父の内面にあったものは、わたしにはわからなかった。
その一週間後、荷造りなどのすべての準備を終えたわたしは、錆びのひどいワゴン車に揺られていた。
学校に行ける最後の日に親友と通った道だった。
別れ際に親友がちょっと恥ずかしそうに微笑みながら、最後にわたしにくれた言葉が胸の奥を行ったり来たりしていた。
〈……“なんか月並みだけど、ずっと友達だからね”……〉
涙が頬を流れていた。
でも、その理由は、その転勤の話を聞かされた日の夜中に母親が泣いていたそれと同じく、わたしにはわからなかった。
ふと窓の外に目をやった。
薄汚れたあの石塀があった。わたしはなにも知らなかった。どんな人が住んでいるのか。なんていう名前なのか。知っているのは、面の粗いあのギザギザした手のひらの感触だけだった。
石塀はあっという間に背後へと一瞬のうちに流れていった。
目で追うようなことはなかった。ただわたしは、いつか切り傷のあったところを指で撫でていた。
高校一年の秋だった。
- 2008年10月31日 04:34
- ──── 『占い』
- Newer: 裏切り : プロローグ & 表紙